遺贈者・受遺者・受贈者の違いとは?わかりやすく整理!
遺言書や相続の話の中でよく出てくる言葉に「遺贈者」「受遺者」「受贈者」というものがあります。
どれも「財産を譲る・受け取る」に関係する似た言葉ですが、それぞれ意味や使われ方が異なります。
特に、「受贈者」という言葉を聞くと、「贈るの?受けるの?どっち?」と迷う方も多いでしょう。
この記事では、行政書士がそれぞれの言葉の正しい意味・違いを図解的にわかりやすく解説します。
遺贈者・受遺者・受贈者の関係とは?
まず、3つの関係を簡単に整理すると以下のようになります。
| 用語 | 意味 | 関係 |
|---|---|---|
| 遺贈者 | 遺言で財産を譲る人 | 財産を「渡す側」 |
| 受遺者 | 遺言で財産を受け取る人 | 財産を「受け取る側(遺言による)」 |
| 受贈者 | 贈与で財産を受け取る人 | 財産を「受け取る側(生前の贈与による)」 |
つまり、
- 遺贈者 →(遺言によって)→ 受遺者
- 贈与者 →(生前の贈与で)→ 受贈者
という関係になります。
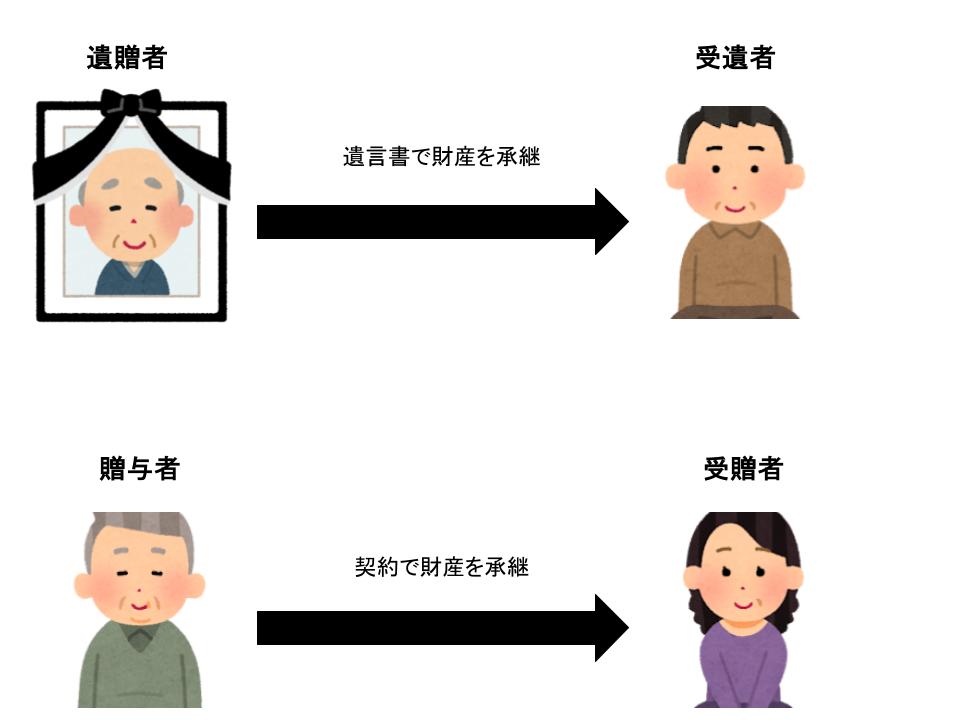
遺贈者とは?
遺贈者(いぞうしゃ)とは、遺言によって自分の財産を他人に譲る人のことです。
遺贈とは、「遺言によって、無償で財産の全部または一部を他人に与えること」(民法第964条)を指します。
遺贈は、相続人以外の人にも自由に行うことができます。
また、相手の同意や承諾を得る必要はありません。遺言者本人の意思だけで成立します。
遺贈の種類:特定遺贈と包括遺贈
遺贈には大きく2種類があります。
① 特定遺贈
ある特定の財産を遺贈するものです。
例:「○○銀行の預金100万円をAに遺贈する」「奈良市の土地をBに遺贈する」
➡ 財産を明確に特定して譲ります。
② 包括遺贈
財産全体の割合を指定して遺贈するものです。
例:「全財産の2分の1をCに遺贈する」
➡ 財産を特定せず包括的に譲ります。
ただし、この場合は負債(借金)も同時に承継することになるため、注意が必要です。
受遺者とは?
受遺者(じゅいしゃ)とは、遺言によって財産を受け取る人のことです。
つまり、遺贈を受ける側です。
受遺者には次の2パターンがあります。
- 相続人が受遺者になる場合(例:長男に土地を遺贈する)
- 相続人以外が受遺者になる場合(例:お世話になった友人に100万円を遺贈する)
相続人以外の人にも財産を譲ることができる点が、遺贈の大きな特徴です。
受贈者とは?
受贈者(じゅぞうしゃ)とは、贈与(ぞうよ)によって財産をもらう人を指します。
贈与とは「当事者の一方が無償で財産を与える契約」であり、相手の承諾が必要です(民法第549条)。
つまり、贈与は契約関係であるのに対し、遺贈は遺言による一方的な意思表示で行われます。
遺贈と贈与の主な違い
| 区分 | 遺贈 | 贈与 |
|---|---|---|
| 財産を渡す人 | 遺贈者 | 贈与者 |
| 財産を受け取る人 | 受遺者 | 受贈者 |
| タイミング | 死後に効力が発生 | 生前に効力が発生 |
| 成立要件 | 遺言のみ(相手の承諾不要) | 契約成立(相手の承諾必要) |
| 税金の種類 | 相続税 | 贈与税 |
| 取り消し | 原則不可(遺言の書き換えで対応) | 合意があれば取り消し可 |
同じ「無償で財産を渡す」行為でも、遺言か契約かによって性質がまったく異なります。
関連する特別な形:負担付贈与・死因贈与
負担付贈与
受贈者が何らかの義務(例:介護や供養)を負う代わりに贈与を受ける形。
例:「介護を続けてくれたら自宅をあげる」
死因贈与
贈与者が死亡したときに効力が生じる贈与契約。
形としては遺贈に似ていますが、契約に基づく点が異なります。
(遺贈=遺言による単独行為、死因贈与=契約行為)
まとめ
- 遺贈者:遺言で財産を譲る人
- 受遺者:遺言で財産を受け取る人
- 受贈者:生前贈与で財産を受け取る人
- 遺贈は遺言による一方的な行為、贈与は契約による双方向の行為
- 税金は、遺贈=相続税、贈与=贈与税が課される

